上京して、もうすぐ4年になる。
カツキ、27歳。九州の片田舎から出てきた。「何かひとつでも成し遂げたい」と熱を持って飛び込んだ東京。だけど、思い描いていた“何か”は、まだどこにも見つからない。
音楽をやりたかった。けれど、バンドはすぐに解散。その後、派遣バイトを転々としながらなんとなく日々をやり過ごす生活。やりたいことも今はよく分からない。ただ、「このままじゃだめだ」と思うことだけは、何度もある。でも、動けない。
夢は霞み、日々はただ過ぎていく。
そんな日々の中で、ある日の夕方。ポストに一通の封筒が入っていた。
『賃貸契約更新のお知らせ』
封筒を手にしたまま、玄関でぼんやり立ち尽くす。天井を見上げると、ところどころ剥がれたクロスと、むき出しの電球。東京の片隅で、一人暮らしを始めた頃は、ここにも希望を感じてた。
「……もう、いいかもな」
ぼそっと呟いた。東京に来た意味って、なんだったっけ。上京してからの4年間が、途方もない空白に思えた。
それでも、答えなんて出るはずもなく。外に出た。なにか気を紛らわせたくて歩いていたら、いつのまにか古びた銭湯の前にいた。
別に風呂が好きなわけじゃない。ただ、あたたかさの中に、なにも考えずにいられる場所があるような気がして──のれんをくぐった。
中へ入ると、番台に座るおばちゃんが顔を上げた。
「いらっしゃい」
その声は、どこか懐かしいような、肩の力がふっと抜けるような響きだった。
「……どうもっす」
カツキが靴を脱いでいると、おばちゃんはじっと彼の顔を見て、ふわりと笑った。
「見かけない子だねえ。ここ、初めて?」
「あ、はい。近くに住んでるんですけど、今日なんとなく」
もごもごと答えるカツキの表情を、おばちゃんは静かに見つめたあと、やわらかく言った。
「曇った顔してるね。……いいサウナあるよ。あったまって、ととのってきな」
その一言に、カツキは一瞬きょとんとした。
でもすぐに、「……はい」と小さくうなずいて、脱衣所へと向かった。
湯船に浸かりながら、ふと目に入ったサウナの扉。「ととのう」ってよく聞くけど、正直、意味が分からない。でも、変わるきっかけがどこかにあるなら……そんな気持ちで扉を開けた。
熱気が、ぶわっと身体を包む。木の香り、じわじわ滲む汗。思っていたよりもずっと暑い。数分で出たくなったけど、意地で座っていた。
そのとき、隣にいた男が声をかけてきた。
「初めて?」
「……たぶん二回目です」
「なら、ほぼ初めてだな。最初はしんどいよ。でもそのうち、気持ちよくなる」
ゆるく結ばれたタオルを頭に乗せたその男は、気負いのない笑顔をしていた。
「ここ、よく来るんすか?」
「週イチくらいかな。サウナ、考えごと整理できるから好きなんだ」
「考えごと、ですか……」
「俺さ、今は映像の仕事目指してて、まだ全然だけど。バイトしながら作品つくって、コンペに出して、落ちて、また作って、みたいな」
「すごいっすね……ちゃんとやりたいことあって」
「正直きついよ。金もないし、周りは結婚や出世して安定してく。たまに、自分だけ取り残された気になる。でも、全部捨てたら終わる気がするから」
その言葉に、カツキの胸がじくりと痛んだ。
「俺、カツキっていいます。九州出身で……なんか東京で頑張りたくて来たんですけど、いまだになんにもなくて。今日、更新の紙見て、もう帰ろうかなって思ってました」
男は、少し驚いたように目を丸くして、それからゆっくりうなずいた。
「アスマ。俺も九州だよ、熊本」
「マジっすか。近いっすね」
アスマは軽く笑ってうなずいた。
「だろ? なんかちょっとだけ、地元の友達と話してるみたいな感じする」
「……そう、だね」
「カツキ、お前も、ひとりで結構踏ん張ってきたんだな」
アスマはタオルで額の汗を拭きながら、静かに言葉を継いだ。
「それ、多分、逃げてもいいタイミングなんだと思う。でもさ、まだ少しでもやってみたい気持ちあるなら、もう一度だけ、足突っ込んでみてもいいんじゃない?」
その一言が、なぜか涙腺に触れた。悔しいとか悲しいとかじゃなくて、もう少しだけ頑張ってもいいのかなって──そう思った。
やがて、サウナを出て水風呂に飛び込む。冷たい水が全身を突き刺す。息が止まりそうになるけど、その一瞬のあと、身体がスッと軽くなるのを感じた。
アスマは歯を食いしばりながら、「っ…つめてぇ…!」と呻いた。カツキはニヤリと笑って、「ほら、根性見せろ。九州男児だろ」と軽口を叩く。
「うるせー、東京もんのくせに!」アスマが言い返すと、カツキはすかさず片手で水をすくい上げ、アスマの肩にパシャッと浴びせた。「ほらよ、愛のしぶき!」
「ふざけんな!」アスマも負けじと反撃に出て、両手でばしゃばしゃと水をかける。二人は小学生のように水を掛け合い、周りの静けさを一瞬だけ破った。
「お前、何歳だよ…」とカツキが笑いながら言うと、アスマは「いや、それ俺のセリフだからな」と返す。
やがて水の音も落ち着き、息を整えた二人は、肩を並べて静かに空を見上げた。どこか懐かしく、あたたかいものが胸の奥に残っていた。
脱衣所の椅子に腰掛け、天井を見上げる。換気扇の音、カランの水音、少し遠くのテレビの音。なにげない生活音がどこか優しく感じられる。
これが、“ととのう”ってことかもしれない。
後から上がってきたアスマが、缶のポカリを片手に声をかけてきた。
「これ、飲む? たまには体にいいもの入れないとさ」
「ありがとう」
缶を受け取って、ゴクリと飲んだ。しみる。普段飲み物にすら何も感じなくなってたのに。
「……おいしい……」
思わず漏れた声に、隣のアスマが即座に反応する。
「だろー? サウナ後のポカリは、もう飲み物っていうか、魂にしみる」
アスマはどこか誇らしげに言いながら、手元の袋をガサゴソと探る。
そして、満を持してオロナミンCを取り出した。
「でも、ここで終わりじゃないんだよな」
「……え?」
「見とけよ」
アスマは半分くらい残っていたポカリのキャップを外し、そこにオロナミンCを一気に注いだ。
炭酸がシュワッと弾ける。簡易オロポが完成する。
「こいつが最強のととのいドリンク、“オロポ”。サウナーの間じゃ、常識」
「えっ、それって……うまいの?」
「飲めばわかる」
カツキは少しだけ身構えながら、そっとボトルを受け取った。
一口、喉に流し込む。
「……あっ、これ……想像以上にうまい……!」
「だろ? 脳にビリビリくるだろ。甘みと酸味と、なんかもう“生き返る感”がすごい」
「やばいっこれ……ちょっとクセになるかも」
ふたりは笑いながら、残りを飲み干した。
着替えたあと、二人は何も言わず喫煙所に向かった。夜風が火照った肌に心地よく、髪をなでていく。
アスマが無言でポケットから煙草を取り出し、自分のをくわえて火をつけた。もう一本を軽く掲げ、カツキに目線を送る。
「……ありがと」
カツキが受け取り、火を借りて一服する。
しばらくの間、二人は黙って煙をくゆらせていた。静かで、でも気まずくない時間。
「サウナって、何も考えずにいられるからいいよな」
カツキの呟きに、アスマが目を細めて煙を吐いた。
「そうだな。でも…俺は逆かも。ああいう場所で、逆にいろいろ浮かんでくる」
カツキは少し驚いた顔をした。
「浮かんできたら、しんどくならない?」
「なるよ。でも、そこで考えないと、多分俺はずっと止まったままになる気がして」
アスマは視線を遠くにやったまま、続けた。
「何が正しいのかなんて分からないし、今やってることが意味あるかも分からない。でも、それでも手を動かしてると、少しだけ前に進んでる気がする。…進んでる”ふり”かもしれないけどさ」
カツキは火のついた煙草を見つめながら、小さく笑った。
アスマはもう一口煙を吸い込んでから、静かに言った。
「俺もさ、まだ諦めてない。情けない日もあるけど、なんとか踏ん張ってる。だから――お前もさ、もしまだやれるって思えるなら、もうちょっとだけ踏ん張ってみろよ」
言葉に力はなかったけれど、不思議と真っ直ぐ響いた。
カツキは何も言わず、煙草を灰皿に押しつけた。火は静かに消えていた。
「……また来るよ、ここ」
「いいじゃん。また一緒にととのおうぜ」
そう言って笑ったアスマの顔が、不思議と記憶に残った。
帰り道、カツキはゆっくり歩きながら、ポケットの中で握りしめたレシートをくしゃっと丸める。
なんとなく、まだ帰りたくなかった。コンビニにも寄らず、まっすぐアパートの方へ向かう。
歩くたび、頭の中でアスマの言葉が反響する。
──「もう一度だけ、足突っ込んでみてもいいんじゃない?」
何度もあきらめかけて、今も何ひとつ形になってないけど。
でも今日は、少しだけ、前より自分のことをマシだと思えた気がした。
ふと、カツキは空を見上げた。
東京の空は、いつも濁ってると思ってた。でも今夜は、少しだけ高く見える気がした。
アパートに帰りドアを開けると、変わらない散らかった部屋が迎えてくる。
だけど今日は、ほんの少しだけ空気が違って感じた。
カツキは靴を脱ぎ、鞄も置かずにまっすぐ机の前へ向かった。
ホコリをかぶったノートパソコンを開き、電源を入れる。
デスクトップに散らばるアイコンの中から、昔のままになっていた音楽制作ソフトのファイルを探してクリックする。
“demo_ver3.mp3”
読み込みのバーが進むあいだ、カツキは小さく息を吐いた。
起動すると、止まったままのメロディが再生される。
──懐かしい。でも、どこか他人の作ったもののような。
イヤホンをつなぎ、ゆっくり音を確かめるように聴く。
なにかを思い出すように、目を閉じた。
「……もう一回だけ、やってみるか」
そう呟いたカツキの声は、さっきより少しだけ、まっすぐだった。
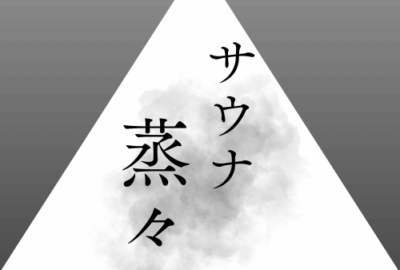


コメント